KIRG 第5回認定講習会 受講感想文
第31期 小林善郎(こばやし歯科医院 佐賀県)
加来先生「ストローマンガイドサージェリーの臨床」
講義ではガイドサージェリーの基本と臨床的応用について解説いただいた。特に補綴主導型の治療計画の重要性、CTとSTLデータを正確にマッチングすることで埋入精度が向上する点を理解できた。フラップレス埋入の適応や、ガイドの支持様式の違いによる特徴も整理でき、ガイドが術者・患者双方のストレスを減らす意義を感じた。今後はシミュレーションとガイドを積極的に活用し、長期安定を見据えた治療を実践したい。
田中先生「審美的インプラント補綴のガイドライン」
審美領域でのインプラント治療における診査・診断の重要性を学んだ。抜歯のタイミングや硬・軟組織のマネージメント、適切な埋入位置やアバットメント形態が長期安定と審美性に直結する点は非常に実践的であった。アバットメントの直径と高さの考察や、粘膜貫通部のジルコニアはグレーズしないことなどが特に印象に残った。今後は補綴設計を含めたトータルプランニングを徹底し、患者満足度の高い審美的治療を目指したい。
武田先生「インプラントを利用した欠損補綴の留意点」
欠損補綴におけるインプラント治療の位置づけについて、原因分析とリスク低減の観点から学んだ。補綴は単に欠損を埋めるのではなく、病因論的に崩壊理由を捉え、咬合関係や支持構造を考慮する必要性を再確認した。慢性疾患としての歯科疾患の特性を踏まえ、治療後も変化し続ける口腔内を見据える姿勢が重要であると感じた。今後はリスク説明を含めた総合的な補綴設計を意識したい。
添島先生「ボーンレベルインプラントの特徴と臨床」
講義ではボーンレベルインプラントの構造的特徴と臨床的利点について学んだ。特にティッシュレベルとの違い、マイクロギャップの位置やプラットフォームシフティングによる骨・軟組織維持の重要性が印象的であった。SLA surfaceによる早期荷重やRoxolid合金による強度向上は科学的裏付けがあり、治療の幅を広げる可能性を感じた。今後は症例に応じた適切なインプラント選択の必要性を意識して臨床に活かしたい。
和泉先生「歯周組織再生治療の最前線」
歯周組織再生治療の変遷から現在の臨床応用まで体系的に学ぶことができた。骨移植、GTR法、EMD、rhFGF-2といった再生療法の進歩に加え、細胞シート工学など次世代技術の可能性も紹介いただき、非常に刺激を受けた。再生治療の評価には臨床的指標だけでなく組織学的な裏付けが重要であることを理解した。日常臨床では適応を見極め、予知性の高い方法を選択していきたいと感じた 。
KIRG 第5回講習会 受講感想文
第31期 平岡 隆(平岡歯科 大分県)
ストローマンガイドサージェリーの臨床 加来敏男先生
インプラントの長期安定に必要な理想的な埋入を達成するためにガイドサージェリーが有用であることを改めて学んだ。ナビゲーションシステムについても改めて学ぶことができた。手製のガイドを用いているが理想的な埋入のため日々考察を行いより理想的な埋入を行うよう努めます。手術見学もよろしくお願いいたします。
審美エリアでのインプラント補綴 必要な術前処置から設計まで 田中秀樹先生
術前の審査により軟組織、硬組織、補綴のデザイン、ポジションについて学んだ。歯肉縁下のエマージェンスアングルについて、バリオベースの高さ、歯肉縁下のグレージングについて講習から帰ってすぐに技工士と話し合いをしました。
インプラントのリスクファクター 長期観察から見えたインプラント補綴の留意点
武田孝之先生
欠損は治療法が一つに決まらない病名。患者さんの何歳までの治療を考えていますか?との質問から始まった講義でした。人生100年の時代、100歳までです。と答えたが特にエビデンスも経験もなく偉そうなことを言ったもんだと恥ずかしい気持ちでした。平均寿命、健康寿命からインプラント治療だけでなく80歳までの治療の計画を立てれるようにならなければと強く感じた。10年は技術・診断。20年は力・病的咬合。30年は加齢・疾病。とのこと。まずは10年。自分の技術と知識の研鑽をいたします。
75歳以上の方への積極的な抜歯についても「真に患者さんのために必要な治療は何か」と考えすぐにとりかかりたいと思います。
ボーンレベルインプラントの特徴と臨床 添島義樹先生
ボーンレベルインプラントを用いることでティッシュレベルインプラントで困難な症例に対応できることを学んだ。プラットフォームシフティングの優位性についても学ぶことができた。
歯科領域の再生治療最前線 和泉雄一先生
歯周組織再生療法の歴史から現在使用されている再生材料を改め学び再生治療のディシジョンツリーによって治療にの選択について整理することができた。また再生治療に用いるフラップデザインについても学ぶことができた。
KIRG 第6回認定講習会 受講感想文
31期 長野 公喜(長野歯科口腔外科 大分県)
ストローマンガイドサージェリーの臨床 加来敏男 先生
ガイドシステムを用いることでインプラントを理想的な位置に埋入することでき、審美的にも、長期間安定した咬合を付与することにも有利に働くことを教えて頂きました。いくつか注意点やこつがあり、例えばCTデータとスキャンデータを正確にマッチングさせる必要があること、遊離端症例ではガイドの安定のために骨支持領域を設けること、直進性の高いドリルの使用など、各ステップの工夫や勘所を学ぶことができました。講演の最後には実際にcoDiagnostiXを用いたプランニングをして頂きましたので、具体的なイメージを膨らませることができました。
審美エリアでのインプラント補綴 田中秀樹 先生
審美的なインプラント治療では、全顎的な治療計画の立案から局所的な軟組織の状態まで配慮する必要があることを、美しい症例写真を供覧しながら教えて頂きました。審美的に仕上げるポイントとして、タイミング、埋入位置、深度、軟組織移植、それらの精度を上げるためのサージカルガイドの利用など、ビギナーである私にとっては難しめの内容でしたが、分かりやすく解説して頂きました。
ケースプレゼンテーション
深町先生と円林先生にプレゼンテーションして頂きました。お二方ともハイレベルな全顎治療をされていて、良い刺激をもらいました。
インプラントのリスクファクター 武田孝之 先生
歯科疾患は慢性疾患であり、欠損治療をする際にはただ補うのではなく、欠損に至った原因を考え、治療後に残るリスクを小さくする必要があることを教えて頂きました。全顎治療は20年安定して経過して初めて評価されるというお話は特に印象的でした。
ボーンレベルインプラントの特徴と臨床 添島義樹 先生
ティッシュレベルとボーンレベルインプラントの違いを詳細に解説して頂きました。ボーンレベルは特に審美領域や近遠心的スペースに制約がある場合に良い適応になり、両システムを使いこなすことで効果的なインプラント治療が可能となることを教えて頂きました。
歯科領域の再生治療最前線 和泉雄一 先生
歯周組織再生療法のお話を中心に、基礎、臨床研究の話を交えてこれまでの治療法の歴史と現在、そして未来の展望までお話頂きました。最近の話題でもあるリグロスと骨補填材の組み合わせなどの話もして頂けましたので、すぐに日常臨床に活かそうと思います。

加来敏男先生「ストローマンガイドサージェリーの臨床」


活発な質疑応答タイム


田中秀樹先生「審美エリアでのインプラント補綴」
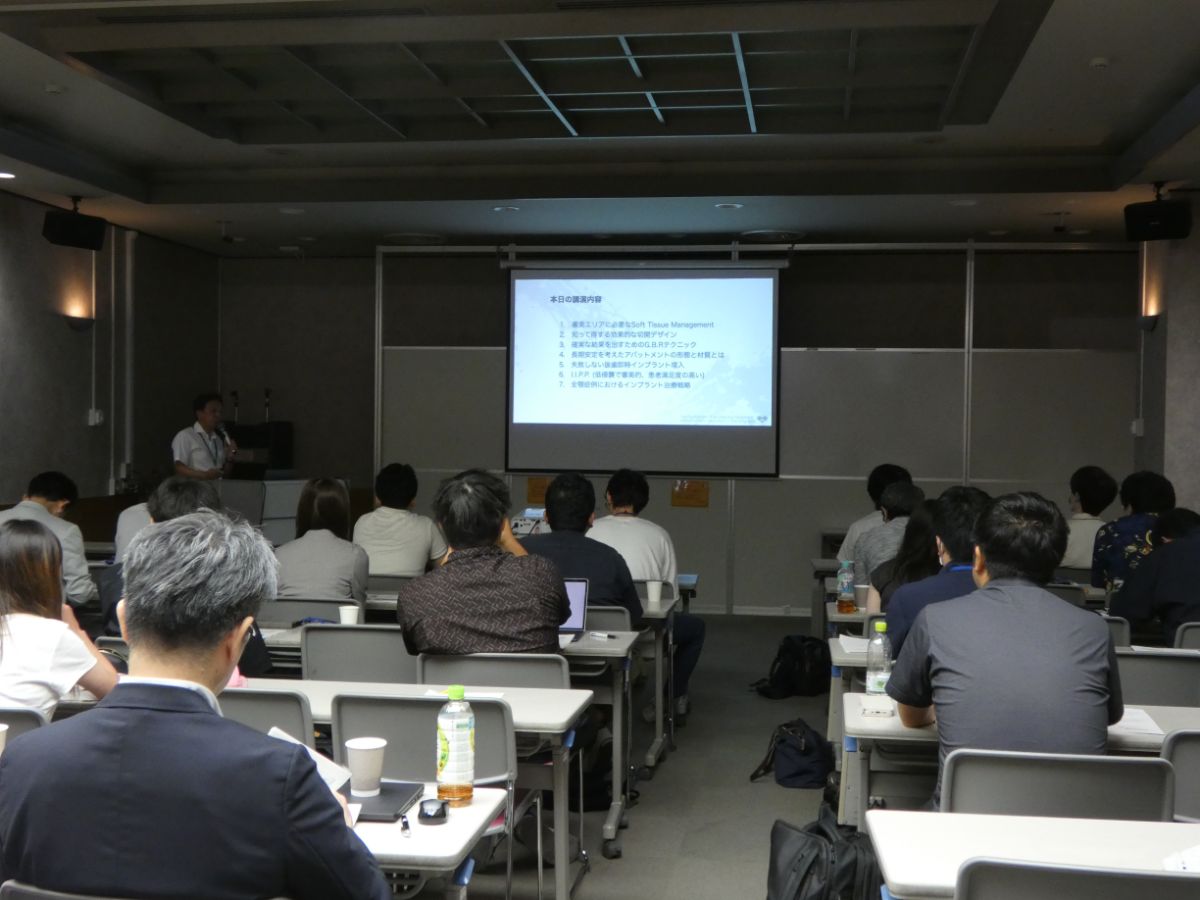

ケースプレゼンテーション「深町太伊地先生」


ケースプレゼンテーション「円林秀治先生」

武田孝之先生「インプラントのリスクファクター」


添島義樹先生「ボーンレベルインプラントの特徴と臨床」

和泉雄一先生「歯科領域の再生治療最前線」

