第7回KIRGを受講しての感想
31期 今村優太 医療法人篤志会さこだ歯科
(鹿児島県鹿児島市)
第7回KIRG(10/18,19開催)に今回も参加させて頂きました。講師陣の先生方や、会員の先生方、事務局の方々のおかげで今回も内容の濃ゆい貴重な講義を拝聴することができました。ありがとうございました。
1日目の最初は飯島俊一先生の「インプラント補綴」というテーマでした。
次は児玉利朗先生のソケットプリザベーションについての講義でした。テルプラグ、テルダーミスを用いた抜歯窩内部だけでなく唇側残存骨と歯肉弁の間にテルプラグを填入するアウトサイドテクニックにはとても感銘を受けました。
次に西村正宏先生の骨造成についての講義でした。ハンズオンの回でも骨造成について学びましたが、より詳しく骨造成についての知見を学ぶことができ、今後の臨床に活かせる学びがたくさんありました。
次に伊東隆利先生の保険適応のインプラント治療についてです。保険適応でインプラントが出来ることについては知ってはいましたが実際にどういう症例があるかや施設基準についての詳しい話を聞いたのは初めてで勉強になりました。
また次の山内健介先生の講義では保険適応のインプラントを現場で数多く経験されてる貴重な講義を聴くことができました。難しい症例が多く、実際の現場での苦悩なども症例を交えて拝聴でき、学ぶことが多くありました。
2日目は小宮山彌太郎先生のブローネマルクインプラントの基本と臨床についてからの講義でスタートしました。長期にわたって患者様との良好な関係を築くためのポイントを抑えることができました。
次に森永太先生の高齢化とインプラントについての講義です。今後我々が直面する高齢化社会にインプラントがどうプラスの影響を与えることができるか、考えさせらる講義でした。
加来敏男先生のストローマンガイドサージェリーの講義ではストローマンのガイド設計について詳しく知ることができました。我々の医院ではストローマンは使ってはいませんが、理想的な埋入ポジションにガイドは必須であると感じました。
全ての講義が濃く、今後に活かしていける内容が豊富でとても刺激になりました。残るところ一回だけとなってしまいましたが、最後まで講師の方々の知識や教えを吸収できるように必死で付いていけるように頑張ります。
KIRG主催日本口腔インプラント学会認定講習会
第31期 第7回感想文
佐藤孝大 (医療法人篤志会さこだ歯科医院)
飯島俊一先生「インプラント補綴の種類と製作法CAD/CAM」インプラント治療の長期予後を追求し、ご自身でインプラントを開発されてきた先生のお話は、まだ経験の浅い自分にとってとても刺激的でした。各インプラントの材料やデザインの特徴を理解し、症例ごとに最適なものを選ぶことの重要性を学びました。特に、インプラント周囲炎やメカニカルトラブル、骨の減少を防ぐ工夫が長期成功の鍵であるという点が印象に残りました。また、先生が考案されたITインプラントの症例紹介では、細いインプラントでも長期に安定していることに驚きました。テーパーロック構造のクラウンは着脱が容易でメインテナンスしやすく、非常に理にかなっていると感じました。
児玉利朗先生「ソケットプリザベーション」講義では抜歯創の治癒様式や分類、リッジプリザベーションの考え方について学びました。抜歯後の創部に対してどのように対応すべきか、バツ字縫合などの具体的な術式を交えて詳しく説明していただき、治癒を意識した処置の重要性を再確認しました。また、創部に使用する生体材料についても、創傷被覆材や抜歯創用止血材などの特徴や使い分けについて理解を深めることができました。特にテルプラグの有用性や実際の使用法についての解説は非常に参考になり、今後の臨床にすぐに活かせる内容でした。
西村正宏先生「骨増生材料の現状と課題」骨増生のゴールドスタンダードである自家骨移植について、その利点とともに採取時のリスクや限界について詳しく解説していただきました。さらに、骨増生に用いられる遮断膜の役割や選択のポイントについても理解を深めることができました。また、骨補填材に関しては、多くの分類や種類が存在する中で、それぞれの特徴や適応を整理して学ぶことができました。加えて、成長因子や血液濃縮液、細胞治療などの最新の再生医療分野にも触れられ、今後の臨床に必要な知識を幅広く得ることができたと感じました。
伊東隆利先生「保険適応のインプラント治療」保険収載されている広範囲顎骨支持型補綴装置や埋入手術について詳しく学びました。特定療養費制度の仕組みや、広範囲顎骨支持型装置の歴史的な背景、保険診療としての位置づけを理解することができました。
山内健介先生「再建によるインプラント」悪性腫瘍により舌や軟組織、顎骨などの硬組織が失われた部分に対し、再建をし、最終的にインプラントを用いて咬合できるようにしていく流れは驚きでしかなかったです。実際の症例を通して手術の流れや臨床での工夫を具体的に見ることができ、非常に勉強になりました。これまであまり触れる機会のなかった保険適応のインプラント治療について、貴重な知識と新しい視点を得ることができた講義でした。
小宮山彌太郎先生「ブローネマルクインプラントの基本と臨床」インプラントの歴史から長期症例、そして歯科医療における倫理まで幅広く学ぶことができました。特に「患者の目先の感謝ではなく、20年、30年先に喜ばれる治療を選びましょう」という先生の言葉が強く印象に残りました。また、長期的に安定した治療を行うための基本や、トラブルを防ぐための考え方についても具体的に学ぶことができ、日々の診療姿勢を見つめ直す貴重な機会となりました。
森永太先生「高齢化とインプラント」実際の症例をもとに、高齢化社会におけるインプラント治療の現状と今後の課題について学びました。加齢に伴う全身状態や口腔機能の変化を踏まえ、治療だけでなく長期的なメインテナンスの重要性を改めて感じました。また、オーラルフレイルの早期発見・予防の大切さを再認識し、OF-5を活用した取り組みを実践していきたいと思いました。今回の講義を通して、歯科医師として患者さんの将来に寄り添う医療のあり方を考えるきっかけとなりました。
加来敏男先生「インプラント治療におけるデジタルの活用」口腔内スキャナーやCT、診断ソフトを組み合わせたデジタルワークフローについて学びました。全てのスキャナーの精度向上や3Dモデルの活用により、正確なガイドサージェリーが可能になっている一方で、デジタルデータを過信せず、臨床的な判断力を持つことの大切さを実感しました。理想的な埋入ポジションを得るためには、正確なCTデータとSTLデータのマッチング、そして骨形態の把握が欠かせないというお話も非常に印象的でした。今後のインプラント治療において、自分の判断とデジタル技術の両立を意識していきたいと思いました。
九州インプラント研究会第31期認定講習会 感想文
藤田愛弓(海のまち歯科)鹿児島
インプラント補綴種類と制作方法 CADCAM 飯島俊一先生
インプラントの上部構造の隣接面形態、インプラントと天然歯の協調、そしてインプラントによる患者の審美面での回復について講義していただきました。そのなかでも天然歯との協調については今後もしっかりリスクも考えながら、長期的に安定するインプラント治療を考えていきたいと思いました。
ソットプリザベーション 児玉利朗先生
ソケットプリザベーションについて講義していただきました。患歯周囲の骨吸収につての診断とその対応については、日々の臨床にすぐ応用できるような具体的な説明をしていただいたので、治癒の過程などイメージしながら処置を行えると思いました。講義後は、通常の抜歯時の縫合も工夫できるようになりました。補填材も特性を知り、症例に合わせて、目的と手段を考えながら、応用していきたいです。
骨増生材料と現状と課題 西村正宏先生
最新の骨増生材料について講義していただきました。とくに最近いろいろな材料が認可されている現状の中、混乱しそうな情報を細かく丁寧に説明していただき、かなり整理することができました。しっかり復習して、日々の臨床に応用していきたいです。
広範囲顎骨支持型装置埋入手術・補綴 山内健介先生
顎顔面領域の疾患による広範囲の欠損補綴についての講義をしてくださいました。衝撃的でした。QOL回復のため非常に大切で、機能させるためにも多職種連携の重要性について教えていただきました。その中でも中心になる人物が技工士さんという点も非常に興味深く、コメディカルの大切さについてより知ることができました。
ブローネマルクインプラントの基本と臨床 小宮山彌太郎先生
インプラント治療の始まりから長年の経験を経て得たオリジナルについて講義してくださいました。インプラント治療は、どんどん新しい技術やインプラント関連商品が発売されている中で、果たして最新のものが本当に良いのか。短期間では良好な結果が得られていても長期的に良い結果を生むかはわからない。患者さんの生体内に異物となりうる生体材料を組織内に置いてくる術式を行うという責任について考えることができました。これからも技術や知識を高めながら実践していきたいと思いました。
インプラントと高齢化・口腔機能低下 森永太先生
高齢化とインプラントについて、長期経過症例や自院内の口腔機能低下症調査などを元に講義してくださいました。インプラントを天然歯の共存のために治療前に欠損歯列の評価を行って、その終末像を予想しながら、治療計画を立てていきたいと思いました。また個人的に当院でも訪問歯科治療を多く行っているので、施設との連携の難しさという点や高齢者への医療の取り組みを見て、とても勉強になりました。
インプラントガイドサージェリーについて 加来敏男先生
インプラントのガイドサージェリーの作成時の注意点などについて、再度詳しく講義していただきました。加来先生の1症例に向き合う熱量というものに驚きと尊敬の念を抱きました。いかにCTとスキャンデータをマッチングさせるのか、口腔内に装着したときにズレがないように行う骨支持について再度学ぶことができました。CTデータをシュミレーションソフトで分析する際に歯肉形態も考慮するために工夫して撮影していきたいです。

飯島俊一先生講義「インプラント補綴種類と製作法」

児玉利朗先生講義「ソケットプリザベーション」

西村正宏先生講義「骨増生材料の現状と課題」

山内健介先生講義「広範囲顎骨支持型装置埋入手術・補綴」
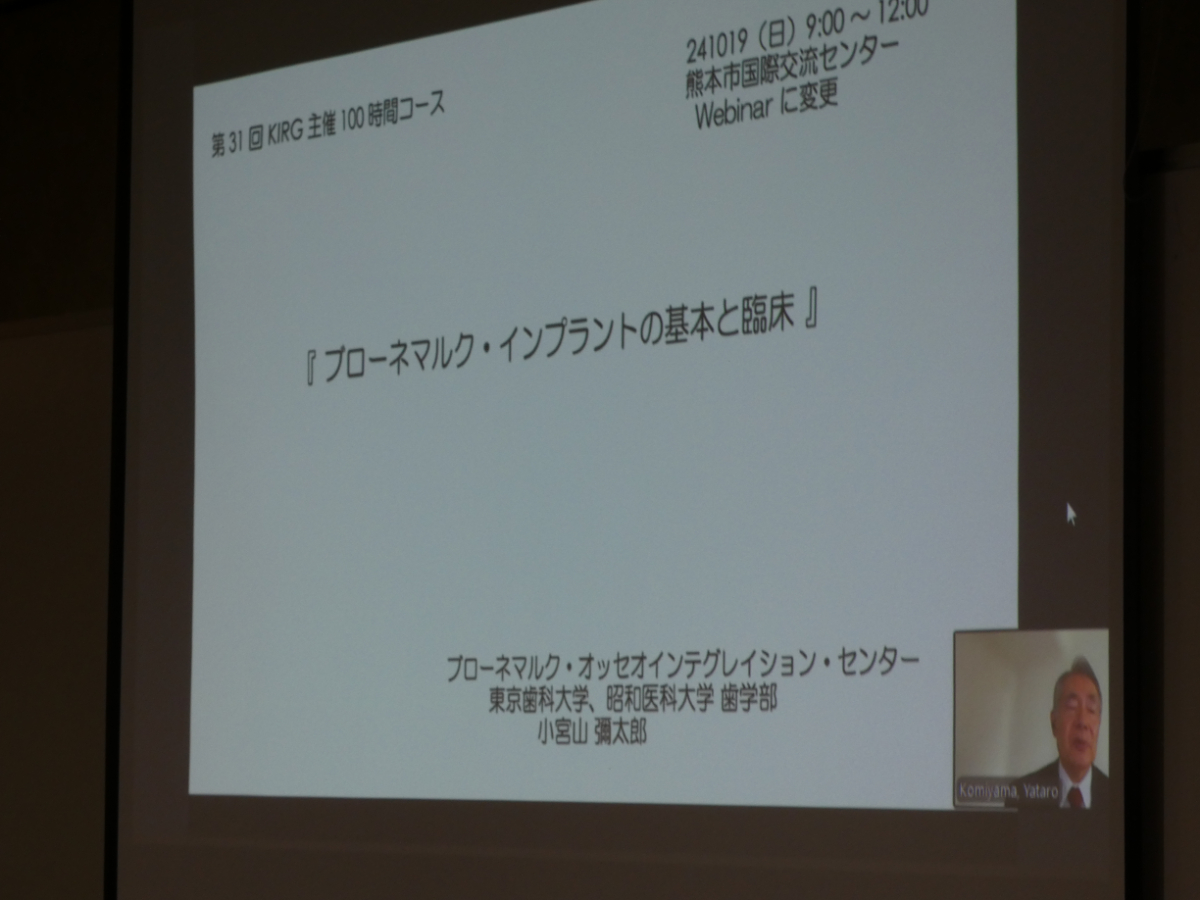
小宮山彌太郎先生講義「ブローネマルクインプラントの基本と臨床」

森永太先生講義「インプラントと高齢化・口腔機能低下」

加来敏男先生講義「ストローマンガイドサージェリーの臨床」

